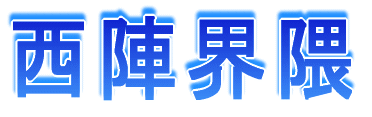西陣織の始まりは,渡来人の秦氏が養蚕と絹織物を伝えたことに始まり,発展していきますが,応仁の乱で荒廃の後,高機(たかはた)の技術を先取して活況を呈していきます。また,応仁の乱で山名宗全の西軍が本陣を置いたことから「西陣」の名が出てきました。
江戸時代になると町人文化の台頭を背景に更に西陣は発展していきますが,幕府の奢侈禁止令,大火や飢饉などのより一時衰退します。明治維新になると進取精神を発揮して,いち早くジャガード織機など新技術の導入を図り近代化に成功,絹織物の一大産地として今日に至り,今でも機の音が聞こえる町西陣は職人の町,庶民の町となっています。
○ 晴明神社
 夢枕獏の小説「陰陽師」をきっかけに,岡野玲子の漫画でブレイクした安倍晴明は,平安時代の天文博士として,また陰陽道の始祖としてここに邸宅があったと伝えられています。
夢枕獏の小説「陰陽師」をきっかけに,岡野玲子の漫画でブレイクした安倍晴明は,平安時代の天文博士として,また陰陽道の始祖としてここに邸宅があったと伝えられています。
しかし,幕末の大火に記録が失われ歴史的にはよく解りませんが,いまも「せいめいさん」と親しまれ,命名や転宅相談に訪れる人の姿が絶えません。
屋根瓦には,晴明桔梗紋が至るところで目を引く。そして,堀川通から鳥居をくぐると,晴明ゆかりの元一条戻橋の親柱に迎えられることでしょう。
しかし,この場所が晴明の宅地跡というのは,怪しくて,安政の大火で社記を消失しており,また明治維新時には危うく廃社になるところを,北隣の斎稲荷社の存在によって残存を許されたということもあった。今の繁栄からは想像もつかないが・・・
○ 黒田如水邸跡
 一条通堀川を西に入り2筋目付近は,如水町でこの町名のいわれとなった黒田如水邸宅跡の石碑を見つけることでしょう。
一条通堀川を西に入り2筋目付近は,如水町でこの町名のいわれとなった黒田如水邸宅跡の石碑を見つけることでしょう。
秀吉のブレーンであった彼は,聚楽第の近くに居を構えていました。
○ あすかの店

NHK連ドラ「あすか」の舞台となった京菓子老舗「塩芳軒」は,黒門通の中立売りを上がったところに店を構えている。店内には非売品ながら「おかめ饅頭」も陳列されている。
西側には,後醍醐天皇の側近名和長年公遺蹟公園があって,地元の聚楽学区では長年出身地の鳥取県名和町と友好関係にあるとか。
○ 一条戻り橋
安倍晴明が式神12体を封じ込めて,用事のたびに使ったとか。
また,この橋はこの世とあの世をつなぐと考えられていたようで,千年前から父親を生き返らせたり,戦時中出生兵士は渡らなかったとか,秀吉が千利休像を磔にしたとか,渡辺綱と鬼女の話,今でも久しい友とこの橋で会うともう会うことがないとか,なにかとエピソードの多い橋である。
一条橋に佇むと,南には中立売通に架かる堀川第一橋が望める。美しい石造りアーチ橋で堅牢な構造となっている。なお,堀川第一橋の南には,路面電車の橋台が残り歴史を感じさせるが,その路面電車北野線は,昭和36年で廃止となった。
○ 武者小路「官休庵」
武者小路通の小川通を東に歩くと,静かな佇まいの中に官休庵が見えてくる。ここの町名は西無車小路町となっている。
武者小路千家は,利休の孫,一翁宗守が立てたもので高松松平家を辞して後建てた茶室のため「官休庵」と号します。
町中のため,幾度も火災に遭遇していますが,庭園は茶庭としての形態を整え表千家・裏千家・籔内家とともに茶庭の代表作となっています。
○ 白峯神宮
明治天皇が,孝明天皇の御遺志を継ぎ明治元年,飛鳥井家の屋敷跡に創建された神社で,飛鳥井家が蹴鞠道の家であったところから,近年ではサッカーブームに乗って球技の神様として人気上昇中です。
境内南東隅にある京都市天然記念物に指定されたオダタマノ木は,樹齢800年といわれ市内最大のもので,幾多の大火を生き抜いてきました。
しかし,この神社はコワ〜イじんじゃなんです。平安末期の保元の乱で讃岐に流されて憤死した宗徳天皇が,死に際して「天地を返してこの国を天皇から取り上げる。」といったとか。その後さっぱり天皇の権威は地に落ちたまま幕末にいたった。
徳川政権から天皇親政を行うにあたって,孝明天皇は千年も前の祖先を神として祀ろうとしたが,志半ばで崩御,次の明治帝によって祀られた正に怨霊を慰めるための神宮なのだ。保元の乱で天皇に参じて戦った源為義,為朝親子も伴緒社として祀られている。
また崇徳天皇と同様に女帝と弓削道鏡の事件で悲運の孝謙天皇も合祀されている。
○ 不審庵・今日庵
 和服姿の方が行き交う通り小川通には,表千家・裏千家の他千家
和服姿の方が行き交う通り小川通には,表千家・裏千家の他千家 十職家が点在し,茶道のメッカとなっている。
十職家が点在し,茶道のメッカとなっている。
表千家不審庵は,千家再興を許された利休の子の少庵が利休の遺跡の不審庵をこの地に移し表千家とした。
同じく北隣の今日庵は,少庵の子の宗旦が隠居所としていた今日庵を四男宗室が告いで裏千家となりました。
 今は暗渠または枯れ川となっているが,小川通には通の由来となった小川が流れこの付近に橋が架けられていたそうな。今は鳴虎の報恩寺前に架かる橋が往時の面影を偲ばせるが,応仁の乱において寺之内通に架かる百々(どど)橋を挟み東西両軍が数度戦った。
今は暗渠または枯れ川となっているが,小川通には通の由来となった小川が流れこの付近に橋が架けられていたそうな。今は鳴虎の報恩寺前に架かる橋が往時の面影を偲ばせるが,応仁の乱において寺之内通に架かる百々(どど)橋を挟み東西両軍が数度戦った。
この付近を百々町といい,人形寺で知られる宝鏡寺は尼門跡寺院であることから百々御所ともいう。
京都の治安を回復した秀吉は,この寺之内通と寺町通に洛中に散在する寺院を集め京都の都市機能の改造活動を展開,近世京都の原形をつくり,今でも両通には多くの寺院が建ち並んでいます。
○ 櫟谷(いちいだに)七野神社
 上御霊前通を西に歩くと,北に空地が開けて鳥居をくぐると小高い樹木が茂る神社に出会う。
上御霊前通を西に歩くと,北に空地が開けて鳥居をくぐると小高い樹木が茂る神社に出会う。
異説もありますが,紫野・上野・柏野・北野・平野・蓮台野・内野を七野といいこれらの惣社と伝えられています。
下鴨上賀茂神社に奉仕された斎王の紫野斎王院の跡という学説もあります。
またここの石垣には家紋が見られることで,これは秀吉に関わる土木工事に多く見られ,あるいは秀吉の命で修復工事に参加した諸大名の寄進印であるともされています。
そして,宇多天皇の浮気に悩んだ皇后がこの神社にお参りして御利益があった事から浮気封じの神としても信仰されています。昭和9年に室戸台風によって櫟の御神木幹が折れ,中から40数本の五寸釘が出て来たそうな。徳川時代の町家で夫の浮気を封じるため,女房が丑の刻参りにワラ人形に釘を打込んでいたのではと伝えられています。
○ 首途(かどで)八幡宮
 智恵光院通を下がっていくと西側に首途八幡宮の鳥居が見えてくる。
智恵光院通を下がっていくと西側に首途八幡宮の鳥居が見えてくる。
平安時代の末期,奥州商人金売吉次の邸跡ともいわれ,源義経が奥州へ下るに際しこの社に道中安全祈願をしたことから,首途八幡宮と言われるようになったとか。
この由来から,旅立ちの安全を祈る信仰が強まりました。
○ 観世稲荷社
 ここは能楽の観世家が,将軍足利義満から拝領した屋敷跡に立つ小さな神社で,場所は西陣中央小学校の敷地内中央南側に有ります。
ここは能楽の観世家が,将軍足利義満から拝領した屋敷跡に立つ小さな神社で,場所は西陣中央小学校の敷地内中央南側に有ります。
広大な敷地も幾たびかの火災によって小さな稲荷社と観世井だけが残されています。この観世水は名水として知られていますが,地下水の合流地点であったため井戸底にはいつも渦が巻いており,この波紋が能楽観世流の文様となっています。
因みにこの場所の町名は,観世町となっています。
○ 本庄家
徳川五代将軍綱吉の生母桂昌院は,堀川の八百屋の娘お玉として生まれるが,数奇な運命から将軍家光の側室となり「玉の輿」のエピソードを残す。世間の批評は必ずしくもよくないが,京都再建に大いに貢献,東石屋町には彼女の寄進した「葵鉾」が残る。
○  山名宗全邸跡
山名宗全邸跡
西陣中央小学校を東の大宮通に抜け,江戸期の西陣の中心地千両ヶ辻と呼ばれた大宮今出川交差を後に北へ歩き,大宮消防出張所を東へ入ると町家の残る街角の中に小さな竹垣に囲まれた石碑が佇んでいる。
ここの町名は山名町で,碑には山名宗全邸跡とあり管領畠山氏の内紛,将軍家の後継問題に娘婿の細川勝元と衝突,応仁の乱を起こした山名屋形の跡地で,西陣の名の由来となっています。
この京都を主戦場とした11年に及ぶ戦いで,当時市街地にあった社寺を陣地として交戦し,そのほとんどを灰燼に帰した。
オチマイ