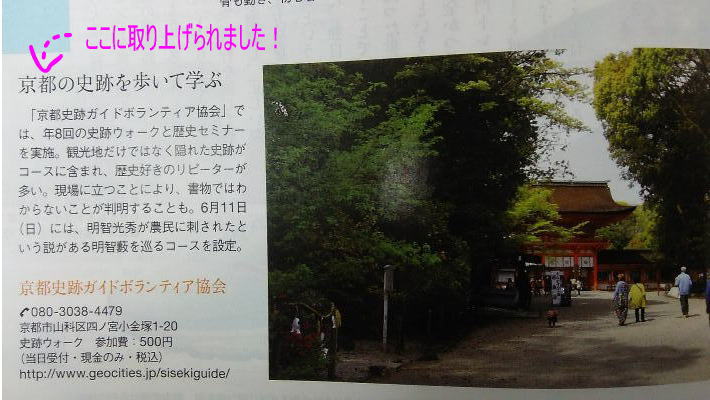六地蔵

法雲山大善寺(六地蔵尊)慶雲2年(705)藤原鎌足の子、定慧(じょうえ、藤原不比等の兄)により創建。仁寿2年(852)冥途から戻った小野篁が六道に迷い苦しむ民衆の為に一本の桜の木に六体の地蔵菩薩を刻み安置した。
その後(1157)平清盛が西光法師に命じて都に通じる5か所の主要街道入口にそれぞれ祀ったところから六地蔵発祥の地といわれ今日まで毎年、8月22日、23日「六地蔵巡り」が行われている。
「六地蔵巡り」① 大善寺 ② 浄禅寺(上鳥羽) ③ 地蔵寺(桂地蔵丹波街道) ④ 源光寺(周山) ⑤ 上善寺(鞍馬口) ⑥ 徳林庵(山科四ノ宮)
「鐘楼」
寛文5年(1665)、108代後水尾天皇の中宮である東福門院(徳川秀忠の娘)が安産成就の御礼に寄進したもの。その時のお子が7歳で即位、109代明正天皇となる。実に48代称徳天皇以来、859年ぶりの女帝。天井には菊と三つ葉葵が描かれている。
「本堂」ご本尊の阿弥陀如来を安置する本堂は勧修寺の宸殿を移築したもの。
「臥龍の松」鐘楼が寄進された同時期に植えられたもので現在は2代目。
小栗栖灸

鍼灸は古く中国で2000年の「黄帝内経」という医学書に記されている。これは漢民族医学書で漢民族との交流で東アジアに広がり6世紀頃に朝鮮半島を経て我が国にもたらされた。
平安期から現在まで我が国の鍼灸は陰陽五行説の論理をベースに発展、今ではスポーツ鍼灸、美容鍼灸なども行われている。
小栗栖鍼灸は温灸、打膿灸の内打膿灸を行っている、打膿灸は悪い箇所を体外に出す方法で、施灸を行う。
寺本灸は現在まで10代続いた「おぐりす灸」で先祖は深草「眞宗院」に自墓を有し、智鏡尼が夢枕に空海が立たれ鍼灸を教えたという伝説を持つ。
現鍼灸師宅にも1800年初期の位牌が並び、祖父母、父母、も鍼灸師であった。
智鏡尼 鎌倉期の尼、京都泉涌寺に住み、後嵯峨天皇の1240年頃中国に渡り蘭渓道隆の来日を促し、中国文化を伝える。
子安地蔵

世に安産を御利益とする地蔵様は数多いが、ここのお地蔵様は日本に三体しかないという、大変ありがたいお地蔵様である。他の2体は、丹波の老の坂と大津にあるのだそうだ。人々から厚い信仰を得ていることは、祠に奉納されている前懸けで十分に理解できる。昔は本経寺そばの祠にあったが、道路拡張のため現在地に御堂を建て直されたのだそうだ。また、祠の前で地蔵盆を行うためにこの地に移した、とも伝えられている。ここは公園で、子供たちが遊ぶのを温かく見守っておられると思われる。
小栗栖八幡宮
貞観4年(862)武内宿祢の子孫である紀古道が関東守護を命じられ下向するに当たり、男山八幡宮の分霊を勧請したことに始まる、この地域の産土神である。紀古道の関東下向に当たってできた社なので、社頭は東向きである。1382神主の地位は飯田民部卿永盛に引継がれ、寛政元年(1789)まで飯田氏が神主を勤めていた。
駒札の「足利時代には社領36石あり」「室町将軍滅亡後は当社も衰え」「地頭は左近将監。左近屋敷は神主で小栗栖城主で飯田家の屋敷であり」「現在は石垣のみ残る」の記載から判断すると、本能寺の変が発生した頃、飯田氏は神主であると同時に武士であり 、城の主でもあったということになる。別の資料によれば、小栗栖城の位置は明智藪の東から小栗栖街道の間とされている。
、城の主でもあったということになる。別の資料によれば、小栗栖城の位置は明智藪の東から小栗栖街道の間とされている。
ところで、小栗栖で光秀を襲ったのは、ただの落武者刈りではなく飯田一族であるとの説がある。これの真偽は不明であるが、一族の中に信長に仕えていた左吉兵衛という者がいて、信長に殉死したという情報があり、これが事実とすると、一族を死に追いやった側の殿様が領地内を通過するとなれば、飯田氏が報復に動いたとしても不思議ではない。また光秀の立場で考えると、織田信長の家来の中に飯田一族がいたことまで知らなかったとしても、ただの落武者刈り以上にリスクが高い場所(現場は城に非常に近い)と警戒すべきだったのではないか。
本経寺

戦国時代の永正3年(1506)日蓮本宗の日法が創建。1658年12世日祐は小栗栖壇林を設立した。壇林とは、仏教僧の学問修業の場である。日蓮宗の僧侶の合同の教育機関として、多くの学僧が集まった。大講堂や経蔵が建てられるなど栄えたが、1713年火事により焼失。その後も活動は続けられたが、明治維新で廃壇。寺内に明智光秀の供養塔が建てられている。
明智光秀の最期については、諸説がある。まず、1582年6月13日夕方、山崎の合戦に敗れた明智光秀は、いったん勝竜寺城に入ったものの勝算はないため、夜陰にまぎれて家臣とともに近江坂本城に向かって落延びる途中、小栗栖の竹薮道で残党狩りの農民・土民または飯田一族の襲撃で深い傷を負った。光秀はもはやこれまでと覚悟し、光秀の重臣・溝尾庄兵衛に「我が首を切り、首は知恩院で灰にせよ。死体は田に隠せ」と言い残し、庄兵衛に介錯させて自害した。ここまでは、違いはない。
この事件のあと、「血竹」といって緑に血の色が混じった竹が生えたので、この竹薮の土地は本経寺に寄進されたという話が伝わる。
明智薮

光秀らを襲ったのは、信長の近臣小栗栖館の武士集団飯田一党であるということと、明智藪が現在は本経寺の寺領であるということを記載している。地元の人の話では、数年前まで説明版は藪地に建っていたが、本経寺が現在地に移したとのことである。小栗栖街道に直接通じる道路の計画がある。
<光秀は領民から愛されていたか>
1571年信長による延暦寺焼き討ちにおいては、光秀は信長の命令の忠実な実行者であった。焼き討ち後、近江国滋賀郡(5万石)を与えられて築城した坂本城は、豪壮華麗なことは安土城に次ぐと言われた。
光秀は、内政手腕に優れ領民を愛して善政を敷いた(自軍の戦死者18名に武者・中間の区別なく供養米を贈る、など)と言われ、現在も光秀の遺徳をしのぶ行事が多い。
光秀は妻木広忠の娘煕子(ひろこ)と婚約した。いよいよ婚礼という時期に煕子は疱瘡に罹り、アバタの顔になった。両親は光秀に恥をかかせてはと思案の末、煕子とよく似た妹を嫁がせた。新婚の床で不審に思った(顔にホクロがない)光秀が尋ねると、妹は経緯を打ち明けた。光秀は「容貌など歳月や病でどうにでも変わるもの。変わらないのは心の美しさだ」と言って、あらためて煕子を迎え入れた。
法琳寺跡

平成12年(2000)から京都橘大学の発掘調査が行われ、礎石や軒丸瓦・軒平瓦が出土した。礎石の柱間は東西3m20㎝、南北2m80㎝で、講堂のような中心的建物であったとみられる。また瓦堆積が検出されており、礎石や土坑は検出されていないものの瓦葺建物の痕跡とすれば鐘楼・経蔵のような小型建物と考えられる。
法琳寺は、白鳳時代に山科盆地で造立された大宅廃寺・醍醐廃寺・小野廃寺などの寺院の一つに数えられる。「入唐五家伝」等の書物によると孝徳天皇の時代(645~54)や斎明天皇3年(657)に開創されたとあるが、発掘された遺物からはそこまで遡ることはできず、675~700年の遺物が最も古い。
中興者とされる常暁ジョウギョウ(?~866)は、838年に派遣された遣唐使に同行した留学僧の一人で、我が国に初めて太元帥法をもたらした。
840年常暁は、法琳寺の地勢を太元帥法を修するに相応しい場所として居住を願い出、御願堂を建立した。斉衡サイコウ年間(854~857)文武天皇は薬師堂を御願として建立、法琳寺は名実ともに御願寺となった。以後、定期的・随時の修法の他、新羅の脅威を除くため(820年)、藤原忠平の病気を除くため(920年)、承平・天慶の乱の際(936年・940年)、その他飢饉を除くためなどに太元帥法が行われたことが記録されている。
常暁が奈良元興寺の僧であったため、法琳寺は元興寺の強い影響下にあった。秋篠寺は法琳寺の別院とされた。1046年常暁の正脈が途絶えた時、曼荼羅寺(現随心院)の仁海が太元帥法を授けたなどの関係から、法琳寺は曼荼羅寺の影響を受けるようになり、さらに鎌倉時代前期には醍醐寺理性院の影響を受けるようになった。法琳寺は鎌倉時代から衰退が本格化し、1313年太元堂が焼失すると、1385年太元堂は理性院で再興され以後太元帥法は理性院で行われることとなって、法琳寺は完全に切り離された。そして法琳寺は室町時代中期に廃絶した。
西方寺

浄土宗知恩院派のお寺である。創建は不明だが、平成元年まで太元堂という、太元帥明王の額が掛けられたお堂があり、堂内には焼け焦げた木像が祀られていた。木像は、法琳寺にあったとされる太元帥明王像または法琳寺開基の定恵像と言われている。お寺は、建築家としても知られる大阪・一心寺の住職の設計で、平成元年改築されたが、太元堂にあった木像は、秘仏として祠に安置されている。正門は、小栗栖壇林の赤門から移されたと言われている。玄関先の水かけ地蔵は、子供たちに親しんでもらおうと造られたとか。
明智塚(胴塚)

光秀が自刃した後、ここに胴体部分が埋葬されたという。首の所在については活発な議論がされているが、胴の議論はあまりない。光秀ほどの武将の亡骸が人知れず田の中に埋められるとは考えにくいため、後世、里人が作った供養塔とも評されている。
<光秀は天海になった…仮説紹介>
天海の出自は不明な点が多い。天海の歴史への登場時期は光秀死後10数年後で、それ以前は明確でない。光秀は信長のやり方には危機感を持っていた。本能寺の変では自分は失敗したが、秀吉の天下統一は定見がない。そこで家康に近づいて徳川の覇権確立に全力を挙げることにした。→「天海」となったとの仮説もあります。
勧修寺

真言宗山階派の大本山で、山号は亀甲山。「かじゅうじ」「かんしゅうじ」「かんじゅじ」と呼ばれ、「山科門跡」とも称される。本尊は千手観音立像。皇室や藤原氏にゆかり深い門跡寺院として知られる。
開創は、第60代・醍醐天皇(885~930、在位897~930)が昌泰3年(900年)、早世した生母・藤原胤子を追善するため、胤子の祖父で、宇治郡司だった宮道弥益の邸宅跡に伽藍を構え、法相宗の承俊律師を開山に迎えて、寺に改めた―との説が有力。寺号は胤子の父で、藤原北家の流れを汲む内大臣・藤原高藤(醍醐帝の外祖父、838~900)の諡号に因む。密教の蘊奥を究めた7代長吏・寛信(1084~1153)が真言小野流一派の勧修寺流を確立。のち、代々の法親王が入寺し、寺格の高さを誇る宮門跡寺院として栄えた。
文明2年(1470)、兵火で諸堂が灰燼に帰したが、江戸時代に皇室と徳川家の援助で復興し、今日の寺観を整えた。宮廷建築の典雅な風趣を偲ばせる堂宇、四季の彩りが美しい庭園が訪れる人々の目と心を惹きつけている。
境内 東側に宸殿、書院(重文)、本堂が並び、西側に庭園が広がる。宸殿は元禄10年(1697)、明正天皇の旧殿を賜った。書院は後西天皇の旧殿(明正天皇の旧殿とも)を貞享3年(1686)に下賜された江戸初期の建築で、一の間の「勧修寺棚」が有名。本堂は寛文12年(1672)、霊元天皇の仮内侍所を下賜された。本尊は醍醐帝の等身像と伝えるが、現在の立像は室町期の作。庭園は「氷室の池」を中心とする池泉回遊式で、四季の彩りが美しい。書院の前庭に建つ勧修寺型灯篭は水戸光圀から拝領した、と伝える。
玉の輿伝説 『今昔物語集』巻第二十二「高藤内大臣語第七」に、藤原高藤と宮道弥益の娘・列子の出会いと、その後が記されている。高藤は南山階で鷹狩りをしていたが、雨宿りのために弥益の家に立ち寄り、勧められるままに一泊。列子に一目惚れし、一夜の契りを結ぶ。2人は長らく音信不通だったが、6年後に再会。列子には娘がいた。高藤との間に宿した子で、この娘がのちに第59代・宇多天皇(867~931、在位887~897)の女御となり、醍醐天皇の生母ともなった藤原胤子。勧修寺の〝前身〟は列子が玉の輿に乗るラブ・ロマンスの舞台でもあった。
今回は、JCBの機関誌、JCB the Premiam 6月号に一部紹介されたことや
ホームページを見られて、明智光秀のご縁の方の参加もあり、参加者141人
会員25人で強い日差しの中を歩きました。お疲れ様でした。
地図は割愛させていただきました。<m(__)m>