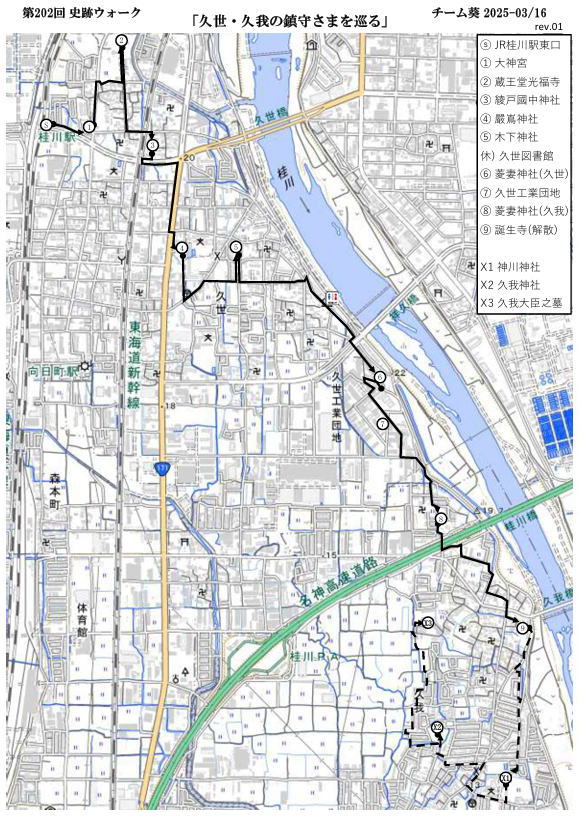大神宮

ここには大神宮社と稲荷社があります。大神宮社には天照皇大神と記されています。この神社 そのものが、伊勢神宮への遥拝所(ようはいじょ)の役割を果たしているようです。また、昔から 村内(現七本松町)の「安全・幸福」の守護神として鎮座していました。 元々この大神宮はこの土地から200m程南にあったのですが、平成10年7月に今の場所に移さ れています。かっての旧社地周辺には巨大な松の老木群があったことから、現在より大きな土地 を有していたようです。
蔵王堂・光福寺

西山浄土宗。955年62代村上天皇のおり、浄蔵貴所の創建とされている。 八宗兼学の道場として栄え、比叡山に対し西南の裏鬼門して王城の守護にあたる。
勅願寺・本尊 蔵王権現。西山浄土宗総本山・光明寺の末寺。 文化財 久世六斎念仏発祥の寺。
綾戸國中神社

綾戸社は、521年(継体天皇15年)の創建と伝えられ、大堰川(桂川)七瀬の祓神として大井社と 称していた。955年(天暦9年)に綾戸社に改称した。古くより上久世の産土神として崇敬される。
國中社は本来蔵王の杜(現蔵王堂光福寺)に社地があって,中世には牛頭天王社とも呼ばれてお り,古くには久世郷全体の郷社であったと推定される。戦国時代に國中社が綾戸社に移され、綾
3 戸國中神社となった。それ以降社殿が並んでいたが、1934年(昭和9年)の室戸台風により倒壊し たため、1936年(昭和11年)に一つの社殿として再建された。
この神社は祇園祭と深い関わりがあり、祇園祭の久世駒形稚児はこの神社の氏子から選ばれま す。
厳島神社

、中久世・下久世の産土神で、国家鎮護・海上交通の守護神として崇めら れていたという。『日本書紀』巻1に、『第一に「田心姫」 次に「立田姫」が生まれ、さらに「市 杵嶋姫」が生まれた。』、と記されている。 主祭神 宗像三女神(むなかたさんじょじん)『市杵島姫神(いちきしまひめのかみ) 多紀理姫命 (たきりびめのかみ) 多岐津姫命(たぎつひめのかみ)』 境内社/摂社・末社 八王子神社 大将軍神社 年當講社 主なご利益 旅行・海上・交通安全 平穏安寧
木下神社

孫瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の妻、木花之佐久夜毘賣(このはなのさくやひめ)を 祀る。瓊瓊杵尊は懐妊し出産期に地上の女ではと疑うが、佐久夜毘賣は高天原の御子だから大丈 夫と部屋に火を放ちながら3人の子供を産む。後の海幸彦、山幸彦(孫は神武天皇)などから安産 の神、防火の神として信仰される。 佐久夜毘賣の父大山津見神は、瓊瓊杵尊に姉の石長比売(いわながひめ)も差しだしたが、容姿 が悪く妹だけを貰い姉を返した。大山津見は姉は石のように永久の命を与え、妹は木の花のよう に一族が栄えるものをと残念がる。
菱妻神社 南区久世築山町

御祭神=天津彦火瓊瓊杵尊(あまつひこほのににぎのみこと) 御神徳=五穀豊穣、商売繁盛、国家安寧、殖産振興など。農業神・稲穂神。 式内社「簀原(すはら)神社」・「乙訓坐大雷(おとくににますおおいかずち)神社」の論社。 社伝には、9世紀中ごろには、式内社「簀原神社」を前身とし、簀原の地に「火止津目大明神」 4 として祀られた。12世紀はじめに桂川の洪水により流失し、その跡地(当地)に簀原大明神を奉 じて鎮座した。火止津目大明神は洪水による流失の後に久我の地に再建されたともあり、これは 現在の久我石原町にある同名の「菱妻神社」のことか? 社名を13世紀頃に「乙訓坐火雷神社」 に、16世紀に「菱妻神社」に変更した。
久世工業団地

、昭和38年京都市に立地していた機械金属関連の製造業に携わる中小企業が、 工場用地の拡大と設備の近代化、経営の合理化を目指して設立し(京都府指定第1号)、今年創立 62 周年を迎える。総面積54,407㎡の敷地に現在22社。総従業員数は750名。立地に当たって は、堤防・道路・畑地等も整備し、ここに京都市内で工場継続に不都合を感じていた企業が集ま った。周辺地域とは建設に関する協定を結び、モノづくりに専念できる環境が維持されており、 また半数近くを30代、40代の経営者が占めていて、全体でまとまりがあることから、会社が 違っても挨拶が交わせる人間関係があるという。
菱妻神社 伏見区久我石原町

御祭神=天児屋根命(あめのこやねのみこと) 天の岩戸で祝詞(のりと)を奏された神。後に天孫降臨に具奉し、祭祀(さいし)をつかさどった神。 神に奉仕される神、文字の祖神、学問の神として広く崇められる。後世の中臣氏(藤原氏)の祖神。 藤原氏・久我家の氏神であり、久我の里の発展と里人達の平和や幸福を守り給う鎮守の神。 平安時代後期12世紀はじめ、1113(永久元)年2月、右大臣 源雅実(=久我雅実(こがまさざね)) 公が奈良の春日大社から天児屋根命を勧請して、「火止津目(ひしづめ)大明神」(火鎮)と奉った。 御遷宮(せんぐう)の時には具仁(ともひと)親王をはじめ、源氏(久我家)・藤原氏の一族が社参し たと伝わる。御鎮座(ちんざ)当時は、神領として当地の近辺に五千坪の地があったと言われ、当 時の広大さがしのばれる。
誕生寺

曹洞宗宗祖の道元禅師の誕生八百年(平成 12 年)にあたり誕生寺として建立された寺で、山号は 妙覚山。全国の信者からの浄財で本堂の他に庫裏、山門、座禅堂、鐘楼、供養塔などが整備され た。道元は聡明利発な少年で14歳で出家、諸方で修行し永平寺に曹洞宗を興す。 5 境内に道元産湯の井戸。禅師が建立した両親の供養塔の復元塔がある。地元では鶴の塔として親 しまれていたという。